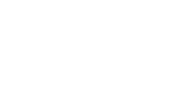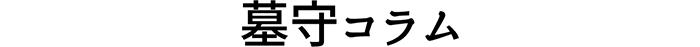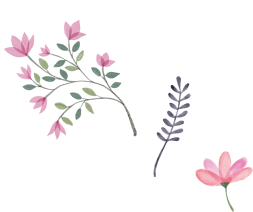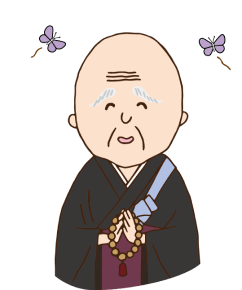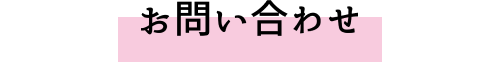ここ最近、ライフスタイルの多様化に合わせてお墓の世界も多様化しています。墓石だけでなく、納骨堂や樹木葬や永代供養など。その中には、お墓を持たずに埋葬すらしない「散骨」も含まれますが、墓守の会は、散骨に断固反対します。他の方法とはあきらかに異なり、私たち人間の幸せに結びつかないからと考えるからです。
私たちは、何のために亡き人を大切に祀るのでしょうか。何のために手を合わせるのでしょうか。何のために生きているのでしょうか。そもそも人間とは何なのでしょうか。
私たちは哲学者でも宗教者もでありません。しかし、お墓を大切に考える、その必要性を確信しているものとして、可能な限りことばに落とし込んで、散骨に反対する理由をみなさんにお伝えしていきたいと思います。
目次
埋葬も墓標もない 散骨は「廃棄処分」である
少し乱暴な言い方になりますが、墓守の会は散骨を「廃棄処分」だと言い切ります。その根拠を綴ってまいります。
人間にとってお墓とは、そこに故人がいて手を合わす場所
お墓というと、墓石のことを連想する人が多いと思うのですが、そこに遺体や遺骨があり、手をあわせる対象があれば、それだけでお墓になります。ですから、樹木葬もお墓ですし、納骨堂もお墓です。いまでも塔婆(故人の戒名などを書いた木の板)を仮の墓標として用いることもありますし、かつてはそこらへんに転がっている形の良い石をお墓としていました。そこに故人が眠っていること。そしてそれを示すもの(墓標)があること。このふたつを満たしていれば、十分に立派なお墓なのです。
ところが、散骨には埋葬も墓標もありません。故人さまを土に還すわけでもなければ、手を合わせる場所もありません。埋葬せずに遺骨を粉末にして海や山に撒くというのは、もはやその人の存在がなかったものとして扱うようなものです。
大自然に還っていくことがもたらす大いなる安心感
たしかに世界を見渡すと、チベットの鳥葬やインドの水葬など、土葬以外の葬法もたくさんありますが、それらはすべて大自然の循環の中に人の亡骸を組み込む形で、ゆっくりと時間をかけて葬られていきます。鳥葬では人の遺体を鳥が啄みます。水葬でも川や海に生きる生物たちが亡骸を養分として摂取します。
火葬した遺骨は、土に帰りづらいという側面もあります。しかし、残された人たちが手を合わせてくれるからこそ、そこにあり続ける価値がありますし、万が一あととりがいなくなったあとには、土の中に埋葬され、時間をかけて自然に溶け込んでいきます。
このように死後の肉体の行方が大自然に溶け込んで循環していくことがわかっているからこそ、私たちは心のどこかに安心感を覚え、亡き人を送り出せるのです。
ちりぢりにされてどこかに消えてなくなってしまった故人
しかし、散骨はそうではありません。焼骨を粉砕機を用いてさらに細かく粉末状にします。もはや土に還る余地も、微生物が分解する余地もありません。しかも粉末状になってしまうことで、風に吹き飛ばされ、海の波間にかき消えてしまい、故人さまがどこにいってしまったのか、その実態を掴めないままです。大自然に還ることもできずに、ちりぢりにされてしまっている状態を、廃棄処分と言わずに何と言えるでしょうか。
肉体の死と霊魂の死 ふたつのバランスが大切
お墓はいらないと考える人からは、「心の中で手を合わせれば大丈夫」という言葉がよく聞かれるのですが、この考え方はとても危険です。心のあり方というものを軽視しています。
武道の世界には「形から入って、心に至る」ということばがあるそうです。いかに人間の心が頼りないものかをよく知っているからこその教訓ではないでしょうか。
私たちは亡き人のことを大切にしながら生きていきますが、どうしても毎日の忙しさに追われて、亡き人のことを忘れてしまいがちです。そんな時に、お墓があれば、故人様やご先祖様に会いに行ける。でも、お墓がない人はいったいどこに向かえばいいのでしょうか。
揺らいでばかりの私たちの心に比べて、お墓、とくに墓石は変わらず動じず、ズドンとそこにいくださる。そしてその土の中では、亡き人の亡骸や遺骨が時間をかけて自然に溶け込むように還っていく。
肉体(遺体や遺骨)と霊魂(心や想い)、この2つをバランスよく弔うことが大切ですし、この2つは切っても切り離せないのです。
人類の歴史は墓から始まった
ヒトは、仲間を葬り、弔うから人になったのです。作家の一条真也さんは『唯葬論』の中で、「埋葬とは「文化(=精神文化)」のシンボルであり、墓とは「文明(=物質文明)」のシンボルであるように思う」と語りますが、埋葬もお墓もない散骨には、文化も文明もありません。
お墓がそこにあるだけで、私たちは安心できるのです。故人の死後を案じなくて済みますし、自分たちの死後に悩むこともなくなります。
なぜなら、その中にご先祖様が眠っていることで「いつか私も同じようにここで眠って、子孫たちにお参りされるのだろう」と、これまで続いてきた「前例」に頼ることができるからです。私たちの命は、私たちが生まれるよりも前から始まり、私たちが亡くなったあとも続いていく。親から受け継いだ命を子や孫につないでいく。そうした命の連続性、人間の本能が、文化を成熟させ、文明を興してきました。
もちろん、21世紀は激動の時代です。死生観や人間観も大きく変わり、これまでのようなお墓ではない新しい形が求められているのかしれません。
しかしそれでも、埋葬と墓標、つまり大自然への回帰と、残された人間による追慕は、未来永劫変わらない人間の営みです。それこそが、人間が人間である所以ですから。だからこそ、この2つをそれぞれ軽視する散骨に、墓守の会は断固として反対するのです。
散骨を選ぶ人たちはさまざまな理由を持っています。
「お金がない」
「大自然に還してあげたい」
「あととりがいない」
「墓参りが困難」などなど。
しかしこうした問題はなにも散骨でなくても解決できる方法があります。ですから、まずはいまあるお墓の取り扱いに困っている人、家族の遺骨の供養に悩んでいる人は、墓守の会にご相談ください。私たちは、ただ「費用が高い、安い」「お墓の管理が面倒、簡単」などのうわべの世界だけで生きていません。あなたの悩みに寄り添い、本当の意味でもっともよりよい、あるべき方法を共に考えていきます。