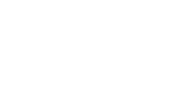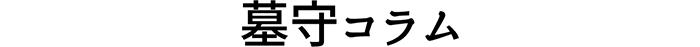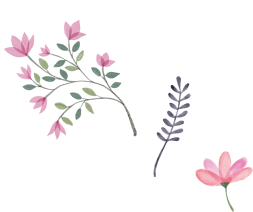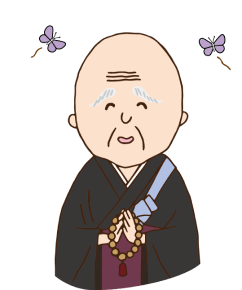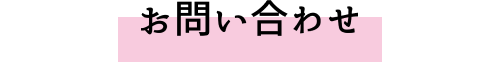墓石のさまざまな箇所に文字を彫刻しますが、その内容は時代とともに少しずつ違いを見せてくれます。この記事では文字彫刻の移り変わりをご紹介いたします。墓石には必ず亡くなった人の名前を刻みますが、彫刻場所は時代とともに移り変わっていきました。その変遷を追いかけてみましょう。
目次
霊標の歴史は浅い
最近では、墓石の横にご先祖様の名前を刻むための板石(霊標)が当たり前になりましたが、霊標の歴史は意外にも浅く、登場したのは戦後のお墓ブームのころからです。もともと戒名は墓石に彫刻していましたが、彫刻スペースが足りなくなったために霊標が使われるようになったのです。以降、霊標はあちこちで見られるようになり、いまでは当たり前のように設置されています。
個人墓、夫婦墓 かつては戒名を墓石の正面に彫っていた

古いお墓を見てみますと、墓石の軸石正面に故人の名前が彫刻されています。これは、そのお墓の中にその人だけが埋葬されていることを意味します。1人にひとつのお墓、あるいは連名にして夫婦で1つのお墓というのが当たり前の時代があったのです。
家墓では、正面に家名、左右に戒名
江戸時代になると、個人墓や夫婦墓があるものの、新たに家墓や先祖墓も登場するようになります。そうすると、墓石の正面には「〇〇家之墓」といった具合に家の名前が刻まれます。これまで正面には刻まれていた戒名は、必然的に左右に追いやられてしまうこととなったのです。
戦後に登場した霊標 ご先祖様の名前を1枚の板石に連ねる
かつてはお寺や地域共同体が墓地を管理していましたが、戦後になると『墓地、埋葬等に関する法律』ができ、お墓を建てる場所に制限がかかるようになりました。登記上「墓地」と認められた場所でしかお墓を建てることはできませんし、墓地の中もきちんと区画整理されるようになったのです。
すると、思い思いの場所に新しいお墓を建てることが難しくなり、ひとつのお墓でひとつの家を数世代に渡って祀る、現代のような「家墓」がさらに一般化していきます。墓石の左右はご先祖様の名前ですぐにいっぱいとなり、こうして生まれたのが、みなさんが墓地でよく見かけるが霊標なのです。
人は、石に名前を刻んで安心する
最近では「家墓」そのものを用いない人が増え、その代わりに樹木葬や永代供養などのような新しい供養スタイルが選ばれていると言われています。
しかし、こうしたスタイルを選んでも、やはり最後は石に名前を刻もうとするのです。永代供養墓の横には故人の名前が刻まれまた板石が設置されますし、樹木葬でも石板プレートに故人の名前を刻みます。
どんなに新しいスタイルが登場しようと、埋葬の際には石への彫刻が不可欠なようです。そこに眠る人を記録するものとして、石が選ばれ続けているのです。