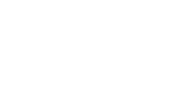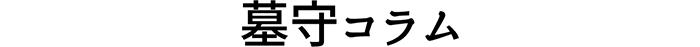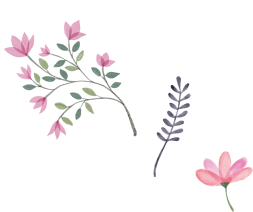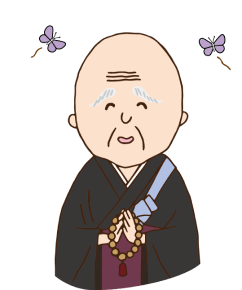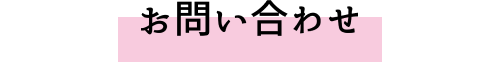もうすぐお盆がやってきます。お盆に欠かせないのがお墓参り。たくさんの人が故郷に帰省してご先祖様のお墓参りをします。お盆の迎え方は地域によって実にさまざま。そこでこの記事では、お墓にまつわるお盆の習俗をご紹介いたします。
目次
迎え火
迎え火とは、ご先祖様を迎え入れるために火を起こす事で、通常お盆の入りの日(8月13日)に行われます。いまでは玄関先や庭先でおがらに火をつけて煙を出す程度ですが、本来はお墓にご先祖様をお迎えに行くという風習が日本全国で見られました。
ここで用いられるのが提灯です。お墓参りをして、そこで灯した火を提灯に移して自宅に持ち帰り、ご先祖様の誘導灯として、仏間の縁側などに吊るしました。
岡山県の美作地方では、初盆のおうちに限り、盆提灯と合わせて108のロウソクを並べる習俗も見られます。
また、ご先祖様のお迎えに用いられるのは提灯だけではありません。長野県箕輪町では、13日の朝にお墓参りをし、墓地の3箇所で火を灯す。ご先祖様を連れて帰る方法に、墓地にある木(赤い椿、サワラ、イチイなど)の枝を持って帰る、おんぶする真似をするなど、同じ地域の中でも家によっても違いが見られるそうです。
共同飲食
お盆にはお墓の前でランチする。そんな地域があります。沖縄地方ではお盆に限らず墓前で宴会をするというのは有名ですが、実は東北地方の北部や九州地方の南部でもこうした習俗が見られます。お墓の前にゴザを敷き、ご馳走を食べる姿はまるでお花見をしているようです。
ただし最近では日本全国で合理的な霊園が普及しているため、こうした光景もあまり見られなくなってしまいました。
ご先祖様の前で共に飲食することで、死者との、そして家族や親族同士の結束を強めてくれます。みなさんも、お墓参りをしたあとに、家族親族揃って食事をしますよね。なんだかあたたかい空気に包まれるのは、ご先祖様がいることでいまの私たちがいるということを再確認できるからなのかもしれません。
h2 安芸の盆灯篭
広島県は安芸門徒といって、浄土真宗が盛んな地域です。県内の墓地や霊園では、お盆になると極彩色の盆灯篭が墓前に並びます。その光景はなんとも鮮やかで、まさに広島のお盆の風物詩。広島にとってのお盆は終戦や原爆を想起させます。と同時に、浄土真宗による阿弥陀信仰の強い地域でもありますので、お墓の前の色鮮やかな盆灯篭に、ご先祖様への極楽往生の願いが込められているようです。
時代が変わる事によって古くから続くたくさんの習俗が見られなくなりました。しかしこうした習俗は、ご先祖さまたちが積み上げてきた、死者と生者をつなぐ架け橋のようなものです。まずはお墓参りをして、いつも以上にご先祖様の存在を身近に感じてみましょう。あなたにとって、素敵なお盆になりますように。
お墓は家族のつながりを再確認できる場所です。お墓参りがあなたの生活を豊かにしてくれます。お墓の維持管理のことでお困りの方、どうぞ墓守の会にご相談ください。